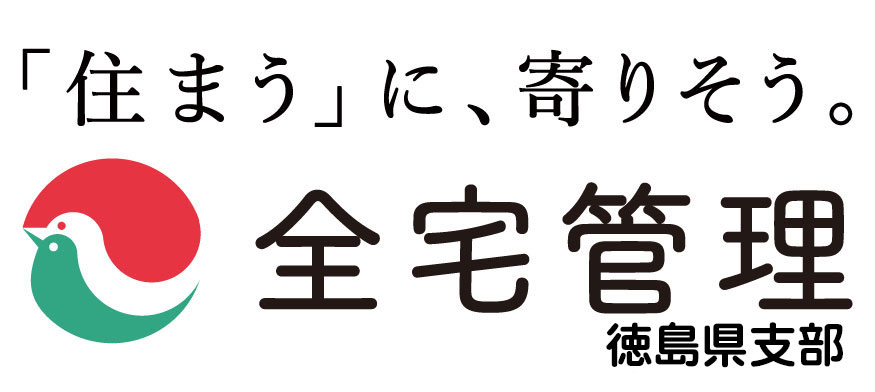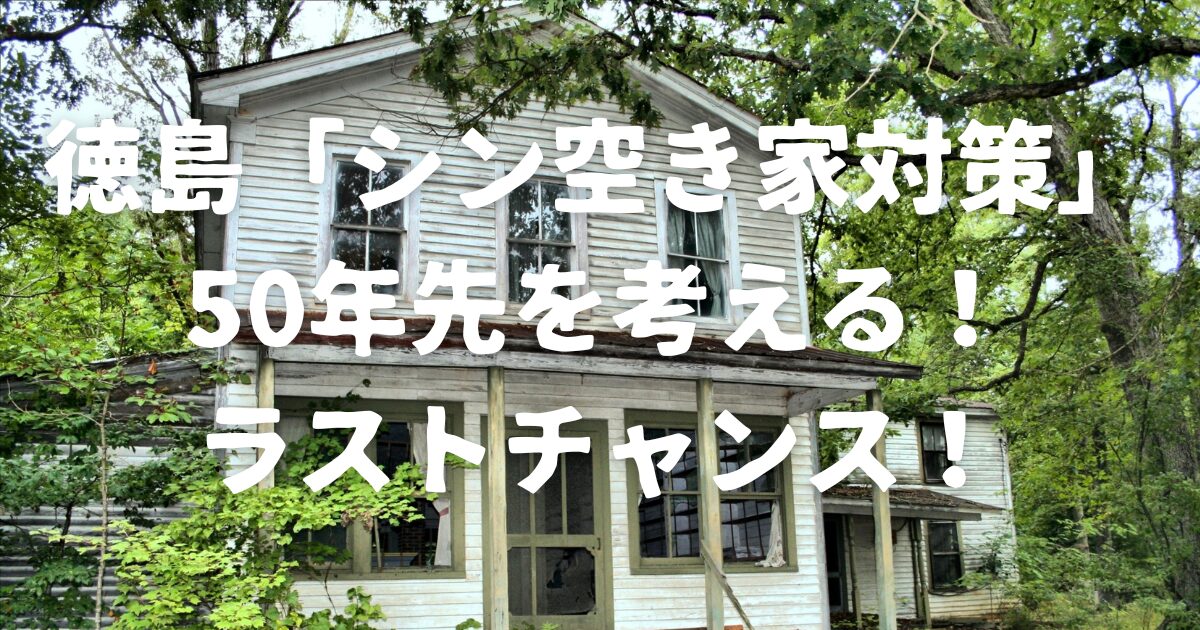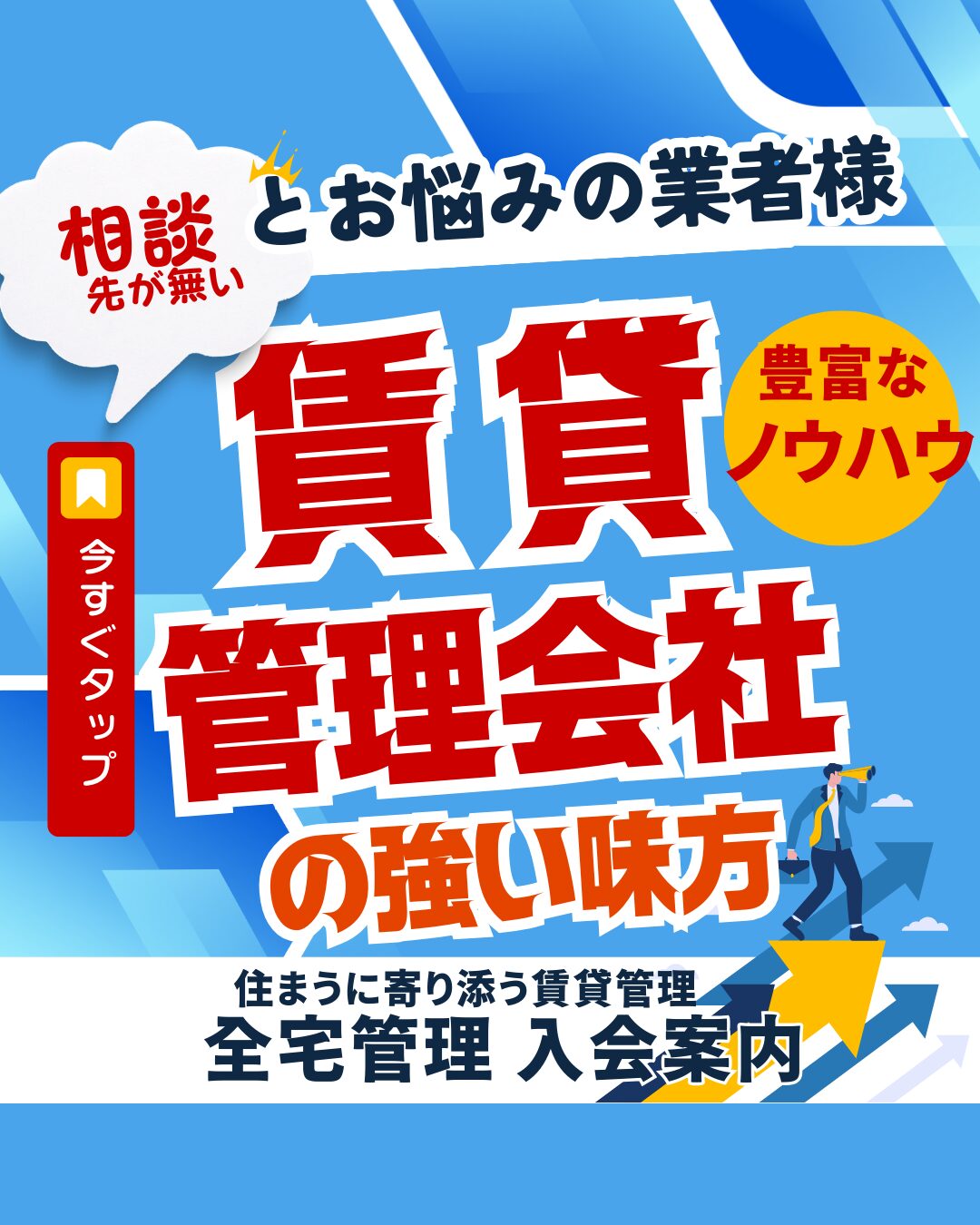はじめに
空き家・空き部屋は、ただの「使われていない建物」ではありません。
放置すれば、防災リスク・景観悪化・近隣トラブルなどのマイナス面が大きくなります。
しかし一方で、工夫と制度を活用すれば「住まい」「観光」「交流」「移住促進」といった 地域資源 に生まれ変わる可能性があります。
徳島県では、総務省の調査によると 約83,000戸の空き家 があり、空き家率は全国平均13.8%を上回る 21.3%。
これは課題であると同時に、地域を活性化させる大きなチャンスでもあります。
徳島県の補助金・支援制度
徳島県および各市町村では、空き家の除却や利活用を支援する補助制度が整備されています。代表的なものをまとめました。
-
徳島県:空き家に関する支援制度一覧
県内市町村ごとの補助制度(解体・利活用)を掲載。
👉 県公式サイト -
とくしま空き家スタイル補助制度
リノベーション補助:最大約320万円
解体補助:最大約80万円
👉 とくしま空き家スタイル -
市町村の例
成功事例に学ぶ
🏠 いもちの家(海陽町)
移住希望者がお試し暮らしできる「移住体験住宅」として空き家を改修。地域住民との交流を生む取り組み。
👉 事例紹介
☕ 古民家カフェ「Cafeオリジン」(石井町)
築100年超の古民家を改修し、カフェ兼地域交流スペースに。建物の雰囲気を活かし、地域に溶け込んだ継続性ある事例。
👉 事例紹介
🍵 茶屋コリトリ(つるぎ町)
築約96年の空き家を茶屋+コミュニティスペースに改修。小規模でも地域住民の交流拠点に。
👉 事例紹介
🏡 落合集落の滞在型ツーリズム(三好市・祖谷地区)
古民家を宿泊施設に改修し、地域文化と観光を結びつける。滞在型観光による地域経済活性化のモデル。
👉 事例紹介
空き家・空き部屋 活用アイデア10選(徳島県向け)
1. 移住おためし住宅・長期滞在住宅
移住希望者が「徳島での暮らし」を体験できる住宅。
👉 ポイント:補助制度の対象になりやすく、移住促進に直結。
2. ゲストハウス・民泊・滞在型観光施設
古民家や空き家を宿泊施設として再生。
👉 ポイント:観光資源と結びつけると収益性アップ。法律面(旅館業法)に注意。
3. 古民家カフェ・地域交流拠点
空き家をカフェやギャラリーに改修し、地域住民と移住者の交流拠点に。
👉 ポイント:地域コミュニティの強化に効果的。小規模でも始めやすい。
4. サテライトオフィス・コワーキングスペース
リモートワーカーや企業の地方拠点に活用。
👉 ポイント:通信環境の整備が必須。都会からの移住ニーズを取り込める。
5. 高齢者向けシェアハウス・見守り住宅
高齢者が安心して暮らせる共同住宅に再生。
👉 ポイント:バリアフリー化・見守り体制が重要。高齢化社会の徳島に合致。
6. 農業体験・体験型観光拠点
農業・自然体験の拠点にすることで観光と教育を両立。
👉 ポイント:農業体験・収穫体験は都市部からの集客に強い。
7. 起業支援施設・ポップアップ店舗
若者や移住者が試験的にビジネスを始める場に。
👉 ポイント:初期投資を抑えてチャレンジできる。地域商店街の再生にも繋がる。
8. シェアスペース(イベント・ワークショップ)
レンタルスペースとして多目的に利用。
👉 ポイント:文化教室、子ども向け教室、地域イベントなど幅広い用途に対応可能。
9. 古民家宿泊+地域体験パッケージ
宿泊と一緒に、阿波踊りや祖谷の自然体験を組み合わせた観光商品に。
👉 ポイント:徳島の文化資源を最大限に活かせる。観光振興に直結。
10. 空き家バンク・マッチングプラットフォーム
情報を公開し、所有者と活用希望者をつなげる仕組み。
👉 ポイント:県や市町村が既に運営中。透明性ある情報提供が成功の鍵。
実現のステップ
ステップ1:物件の調査・診断
まずは空き家の現状を把握することが最優先です。
-
建物の安全性チェック
-
屋根・外壁の損傷
-
シロアリや腐朽の有無
-
耐震性・断熱性
-
-
法令制約の確認
-
建築基準法(用途変更の可否)
-
都市計画・用途地域
-
景観条例や文化財指定の有無
-
ステップ2:所有者・地域との合意形成
-
所有者が遠方在住の場合も多く、相続人が複数にまたがるケースも。権利関係を整理することが必須。
-
地域住民の理解も不可欠。宿泊施設やイベントスペースにする場合、近隣への説明会や合意形成が必要です。
👉 徳島県では「空き家バンク」制度を通じて所有者と利用希望者をマッチングしており、地域合意のサポートも受けやすいです。
ステップ3:資金計画の策定
-
補助金の活用
-
とくしま空き家スタイル:最大320万円(利活用)、最大80万円(解体)
-
-
民間融資やクラウドファンディング
-
宿泊施設やカフェなどの場合、クラウドファンディングで「応援消費」を取り込む事例も増えています。
-
👉 初期投資+維持費を含めて、5~10年で回収できるかが目安。
ステップ4:改修・設計
-
安全性の確保
-
耐震補強、バリアフリー改修、断熱工事、電気・水道の引き直し
-
-
魅力を活かすリノベーション
-
古民家の場合は梁や土壁を活かす
-
現代的な機能(水回り、Wi-Fi)を整備
-
👉 補助金を申請する場合は「工事前の現況写真」と「設計図面」の提出が必要なことが多いので、最初から撮影・保存を徹底しましょう。
ステップ5:運営体制の整備
-
日常管理
-
清掃・ゴミ処理・庭木の手入れ
-
-
契約関係
-
賃貸借契約か、利用契約か
-
保険(火災保険・施設賠償責任保険など)
-
-
人材確保
-
宿泊施設なら清掃人員
-
カフェなら運営スタッフ
-
コワーキングなら管理者
-
👉 NPOや地域団体と連携して「共同運営」することで、運営負担を軽減する事例もあります。
ステップ6:集客・プロモーション
-
地域資源と結びつける
-
祖谷地区では「古民家宿泊+かずら橋観光」
-
海陽町では「移住体験+地域農業」
-
-
情報発信
-
空き家バンク・自治体サイトに掲載
-
SNS(Instagram、X、Facebook)で写真・動画を発信
-
AirbnbやBooking.comなど宿泊プラットフォームを活用
-
👉 Airbnb Japanと徳島県の「空き家5戦略モデル事業」では、空き家活用を観光振興と直結させています。
ステップ7:持続可能性の確保
-
利用者の声を集めて改善
-
季節変動を考慮した料金・イベント企画
-
地域住民や行政と定期的に協議
-
維持管理費を確保するための「複合用途」(例:平日はコワーキング、週末は宿泊)
👉 成功事例の多くは「単独用途」ではなく、「多機能活用」で収益と地域貢献を両立しています。
補助金や制度を上手に組み合わせ、地域の声を取り入れながら進めることが、徳島での空き家再生成功のカギになります。
まとめ
-
空き家・空き部屋は「地域課題」であると同時に「地域資源」。
-
成功の鍵は 用途設計・制度活用・地域との協力。
-
補助金・助成金を上手に活用し、小さく始めて持続可能な活用を目指しましょう。